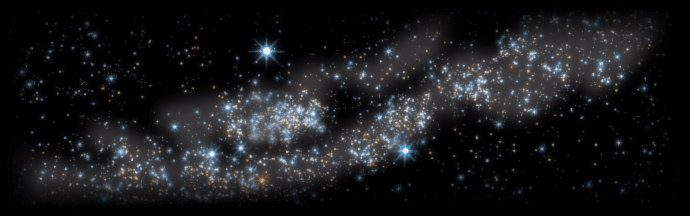星降る、その夜に___MWU SIDE.
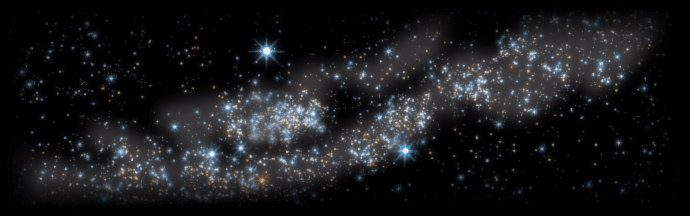
ひかりが、空から降り注いでいる。
忌々しいほどに、夥しいそのデブリの雨は、予測の範囲を遙かに超え…俺たちはここに足止めを食らった。
デブリの雨。
地球の引力に引かれて、夥しい金属片が帯のように集まり、周期的にそれは地上に流星となって落ちてくる。
その流星雨はときに電離層に磁気嵐をもたらし、太陽風と同じレベルで電子機器や通信に影響する。
俺は、早々にこの場所を離れるつもりでいたのだが。
予定していた輸送機の便が、この状態では飛べないことがわかった。
陸路を取ったとしても。
目的地まではあまりにも時間がかかりすぎる。
諸々のことを検討した結果、デブリの流星雨が収まるであろう明日の午前まで、意に反してこの施設に留まることになってしまった。
ロドニア___旧世紀、ギリシャと呼ばれたこの土地に、その古びた施設があった。
いや。
古びて見えるのは要塞、城郭とおぼしき外観のみ。
秘密裏に構築された研究施設の規模とレベルには、正直驚いた。
「ラボに行け。使える子供を見繕ってくると良い」
あの男が言った。
子供。
エクステンデッドの、子供。
自分がナチュラルだ、と言うことは”知っている”。
戦う相手が、遺伝子操作をされた種・コーディネーターだと言うことも。
俺は”知っている”。
しかし。
その種に対抗するために。
ナチュラルの子供を、「調整」する、やり方が、正しいのだろうか___?
薬漬け。
記憶の操作…洗脳。
ロドニアの”ラボ”。
ここで。
取り澄ました大人達が、それを、淡々と”業務”として遂行している
反吐が出そうだ。理由は、自分でもよく判らない。ただ。生理的に、その行為が…自分では受け付けないことだ、と思った。
手渡されたリスト。
そこには表情の乏しい子供が、瞳を濁らせて並んでいた。
何を、どう”操作”して、その能力がどう伸びたのか。
そんなことがデータとして添付されている。
戦争を、していた___。
俺は。
この、星の降る空の彼方で。
コーディネーター…プラントの擁するザフトと、戦争を、していた___覚えている、というにはあまりにも曖昧だが。
軋む身体の傷は、そのときに負ったものなのだ、という自覚はあった。
顔にも負った傷。
それを隠すために仮面を付けて過ごすようになって…どのくらい経っただろう?
違和感のぬぐえないそれを見て、たいていの相手は身構え、遠巻きにする。
それでいい、と俺は思っている。
なれ合う必要はない。
戦争をするしか能のない軍人は、なれ合いでは生き延びることはできない。
だから。
必要なことが伝われば十分だし。
鬱陶しい関係を結ぶことなど、俺にはなんの価値もない。
与えられた任務を滞りなく遂行し。___勝つ。
それだけが、今の俺の存在意義だった。
だが。
こんな子供を使わなければ勝てない戦争…それは、俺にとっては違和感の塊でしかない。
ばさ、とテーブルにファイルを投げつけたら、間に合わせで俺につけられた副官が驚いて立ち上がった。
「ロ、ロアノーク大佐?!どう…」
まだ若い中尉だ。几帳面に、まるで齧歯類の小動物のようにちょこまかと動き回っているかと思うと、始終携帯端末を開いて某かを打ち込んでいる。どうせ、こいつもあの男___ロード・ジブリールの配下で、俺が何をするか見張ってるんだろう…。
何をするつもりもないが。
監視をつけられるということ自体、ぴりぴりと嫌な感じが肌にまとわりついてくる…。
「明日は発てるのだろうな?」
こんなところに長居はしたくない…。
静かに問うた筈が。
ヤツには恫喝のように聞こえるのだろう。
まあ、無理はない。
「確認…致します」
そう言うと、ヤツは部屋を飛び出していく。
一人になって、俺は溜息をついた…。
澱んだ空気。
閉塞感。
照明を落とし、与えられたやたらに広い居室の窓を開くと、そこは建物にぐるりと囲まれた中庭になっていた。
幾何学模様のような作りの庭。
どこかで見た…ああ、ジブリールの屋敷の造りに、少しばかり似ているが。
決定的に違うのは、すべてが石造りで組み上げられているところだろう。
月明かりよりも眩しいひかり、まがい物の流れ星が降り続けるその空の下、まるで昼間の明るさのような陰影が見て取れる。その中を、まるでじゃれ合うような人影が映った。
なんだ?
華奢な影が一つ、それを追うように駆けてくるのが二つ。
石畳の中央に立ち、首が折れそうなほどに上を向いて空を見上げていた。
「きれーーーーぇい!ねえ、ひかりの雨がふってくるみたい!」
女?いや、子供、と言うべきか。ずいぶんと無邪気に、石畳の上をくるくると踊るようにステップを踏む。
「静かにしろよ、見つかったらやばいんだから」
その少女をたしなめるような少年の声。
「だぁいじょーぶだって。こっちは明かりがついてないだろ?滅多に使われない棟なんだからさ」
もう一人の少年の声が、暢気に諭す。
俺の気配には気づいていない、ということだろう。
そうこうするうちにその二人が地面に転がった。
「ホント!まるで、星の雨が降ってくるみたいだぜ」
大きなデブリが燃え尽きたのだろう、ひときわ白くなった空に照らされて、彼らの顔が見えた。
…ファイルにあった顔だ。
それぞれが”特Aクラス”と推薦されていた。
しかし、施設の中で見た訓練風景の中で、彼らを見た、という記憶は薄い。
きっと。
どの子供も同じように、あの空間では”個性”が無くなり、周囲に溶けてしまうのだろう。
殺戮者、と言う名のパーツと化して。
「なあ、モビルスーツで宇宙に出たら、こんな風に星の海に浮かんでるように見えるのかなぁ?」
「さあ…どうだろうな」
踊る少女の髪が広がり、腕を空に向けて…まるで星を掴もうとするかのように背伸びをした。
その姿に。
俺はなぜかくす、と小さな笑みを誘われた、…ことに驚いた。
ふいに___警報が鳴り響き、中庭に強烈な照明が当てられた。
三人の姿が露わになる。
踊っていた少女が凍り付いたように立ち竦み、少年二人が跳ね起きた。
周囲を、銃を持った重装備の警備員が取り囲むのが見えた___。
取り押さえられた華奢な少年が壁際にうずくまっていた。
骨張った傷だらけの手首には黒い手錠がはめられている。
眩しすぎるほどの照明の中で、殴られた頬のアザと口元を拭った血の名残り、おそらくはスタンガンの火傷の痕だろう…赤く腫れた首筋が日焼けとは無縁の青白い肌に痛々しく映った。
しかし…顔を覆うように乱れた前髪から覗く瞳は戦意をまだ失っておらず。
周囲を威嚇するように力を漲らせていた。
「名前は?」
俺が問うても、その少年はぷい、と横を向いてしまい、傍にいた警備員が腰に付けた特殊警棒を手にするのを見て、またぴくりと震え、唇を噛みしめた。
「大佐の質問に答えろ」
そう、副官が俺の威を借りて下問するのはあまり良い気分のものではない。
俺はヤツを制して、少年の前に膝を落としてかがみ込み、顔をのぞき込んだ。
…といっても。
仮面が邪魔して、少年には俺の目は見えない。
「…アウル・ニーダ」
その反抗的な態度に、背後でまた数人が動く気配があったが。
俺はそれらを制し、彼に正対した。
「俺と一緒に来るか?」
瞳が、大きく見開かれた。
咎めるような声が背後で起きた。
俺は立ち上がり、そこにいたラボの主任だという男に向き直った。
「リストに載っていたな?だったら、俺がこいつを引き取っても問題はあるまい」
「しかし、大佐?!」
「こいつらが一体何をした?どうしてこうも制裁を受けなきゃならんのだ?」
鼻白むラボのスタッフが言いたいことを飲み込もうとして拳に力を入れたのが見えた。そいつの顔には、ひっかかれたと思しき傷が二筋ついていた。
「…処分、というのならこいつらはどうなるんだ?」
「ここまで”教育”が進んでいるコンディションで、我々の指示を守らない場合は、最悪、廃棄となります」
廃棄?
その言葉がわかっているのかいないのか。”アウル”は全く反応しない。
「なら、なおのこと、だな」
手錠を外すように告げ、少年の腕を取って立ち上がらせた。遠巻きにしていた警備員が銃を向けようとしたのを、副官が遮った。
「ステラと、スティングは…」
「え?」
「あいつら、どうしてるんだろ…?」
俺が視線を巡らすと、苦々しい、と言った表情のスタッフが、主任研究員に耳打ちした。
「他の二人は?」
「メンテナンスベッドで、薬で眠らせています」
危険だったので…と連中は言った。
「落ち着いたら、大丈夫なんだろう?」
「まあ、調整を実施しているところですので…もうすぐ目覚めると思われますが」
ならどうして、ここにアウルだけが酷い状態で置かれているのだろうか、と思いを巡らせる___虐待?…スタッフの、憂さ晴らし…軍では、よくあること…反吐が出る。
最低、だな…まあ、この子供達をここから出したとしても、ただ場所が変わるだけ…命をすり減らす最前線に送り込むこととなれば…俺も人のことは言えないかもしれないが。
「来るか?」
そう問うた俺を、アウルは不思議そうな顔をして見上げた。
「どこへ…?」
後になって。
彼らはその意志を問われる、ということが無かった___命令されたことを遂行するのみ、という行動プログラムを刷り込まれていたのだ、と知った。
「星が見たいか?」
おそるおそる、と言った表情で彼は頷いた。
「なら…宇宙(そら)へ、上がるか。他の二人も、一緒に」
笑顔を、初めて見せた。
”子供”らしく…瞳の色を、きらめかせたのを見た。
それから、何年が経っただろう。
あの日、12月24日がクリスマス・イヴだったのだと判ったのは、記憶を取り戻してからだ。
俺と出会うことなく。
あのまま…あそこにいたら、あの子供達は一体どうなっていただろうか。
他に、どんな生き方があっただろうか…?
サンタさんがくるよ、だから早く眠りなさい…と言って、幼い息子や娘を寝付かせるとき。
あの星の降る夜を思い出す。
骨も残らぬような死に方をさせてしまったのは、俺だ。
最期が、どんなだったかもしれぬような…寂しい死を…。
我が子の、頬にキスをして、ブランケットをなおしてベッドを離れる。
薄明かりの中ドアを閉じて階下に降りると、そこにマリューがいてくれる。
もしも。
あの三人がここにいたら、どんなだっただろう。
埒もないことを思う。
もしも。
人が生まれ変わると言うことが叶うのならば。
おまえたちをしあわせにしてやれただろうか?
…バカか、俺は…。
「どうしたの?ムウ…」
…おまえたちは、しあわせだっただろうか?
「なんでもない…」
雪も降らないこの土地で、クリスマスを祝うのは一体何度目だろう。
いつか。
君に語れる日がくるだろうか。
あの子供達のことを。
あたたかいマリューの頬にくちづけて。
俺は”今”を抱きしめる。
忘れない。
そして、いつか…あの日のことを君に語ろう。
窓の外。
ひう、と星が流れた。
潮風の匂い。
静かな夜。
静かに、星は降り続ける。
この作品の雰囲気が何とも言えず大好きです。
対の作品がこちら