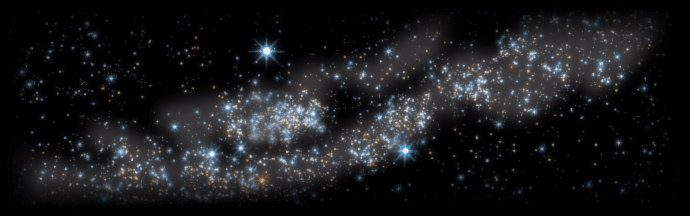星降る、その夜に___MURRUE SIDE.
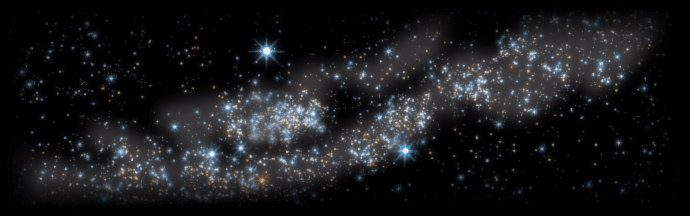
空を仰いで胸一杯に潮の匂いを吸い込む。
静寂。
波と、わずかに木の葉を揺らす風の音。
そして、私は空から零れんばかりに降り注ぐ光の雨を見上げた。
デブリの雨。
地球の引力に引かれて、夥しい金属片が帯のように集まり、周期的にそれは地上に流星となって落ちてくる。
ことに、赤道付近にはその事象が多く。
オノゴロを含むオーブの上空も例外ではない。
戦争の負の遺産。
しかしそれは、皮肉なことに…とても美しい。
その流星雨はときに電離層に磁気嵐をもたらし、太陽風と同じレベルで電子機器や通信に影響する。
予報は出ていたものの…その規模が予想外に大きかったということで、モルゲンレーテの工廠は軍の指令で異常事態発生に備えて待機___つまるところ、仕事が突然キャンセルになってしまった。
それは、幸いだったのだろうか?
ぽっかりと時間が空き、喜々として帰宅の仕度をし始めたエンジニア達が言った。
”クリスマス・イヴだから…もしかしたらサンタ・クロースが気を利かせてくれたのかもしれない”と。
彼らは、家路を急ぎ…きっと家族や恋人達と、思いがけなくたっぷりと過ごせることになったイヴの夜を楽しむのだろう。
私は、といえば。
今日がその日だという概念すら、頭の中から消してしまうほどに…仕事に没頭していたのだ。
それが、今の自分にとっては一番楽な時間の過ごし方だったから。
「ラミア…じゃねえや、ベルネス主任は、どうします?これから整備の連中と飲みに行く話になったんすが…」
マードック曹長…今は”マーカス技師”が私に声をかけた。
ここには何人もの、昔なじみが働いている___それぞれに与えられた、昔とは異なる名前で。
「ありがとう。でも、もうちょっと家でやっておきたいことがあるから…みんなで楽しんで頂戴」
そう言うと。
彼は小さく肩をすくめて笑った。
「ちゃんと休んで下せえよ…じゃあ、メリー・クリスマス」
その言葉が、彼のいたわりの気持ちを滲ませて、耳に届く。
「ええ、…ありがとう、メリー・クリスマス」
今は、もう、軍人ではないから…敬礼は必要ないのに。
彼と…その場にいた数人が帽子を取り、姿勢を正す。
私は小さく手を振ってその場を離れた。
クリスマス。
神の子の生まれた日。
私は洗礼は受けたけれど、実質…無宗教も良いところだ。
神様の存在を疑うわけではないけれど。
だからといってそれを全て肯定はできない。
神様は、ただそこにいるだけ。
人の世に関与するわけじゃない。
この日に、そんなことを考えたらバチがあたるかしら?
帰路、私はいつもよりゆっくりと海岸沿いの道を運転した。
…月夜の明かりよりも遙かに眩しいほどの、まばゆい光が、空からこぼれていた。
「お帰り、マリュー」
数日ぶりに戻った屋敷の中は、いつもと全く変わらない。
そして玄関ホールのむこうのリビングにいる男の風情も全く変わることはない。
「ただいま」
そして、ひと息おいて、思い出したように言ってみた。
「メリー・クリスマス…」
おや、と言うようにバルトフェルドは眉を上げた。
「夕食は取ったか?」
「ええ」
「軽く、だろ?」
私は、困って曖昧に微笑んだ。彼はいろんな意味で私のことはお見通しだったりする。だから、ごまかすことができない…。
「姫から、差し入れがあるよ。マーナ女史が昼間に持ってきた。よろしかったら食後にぴったりのコーヒーもお入れしますが?…どうするかね?」
「…まあ!」
カガリさんとも随分会っていない。とはいえ、それは当たり前だ。
彼女は今は多忙を極めた生活を送っている。たまにニュースを見ると、いつもいつも厳しい顔をして戦っている。
先の大戦から一年余り。
亡き父上のご意志を継いだのだ。そんな彼女が、ここにいる私達に、そんな心遣いを見せてくれたのだと言うことに驚き、そして、嬉しかった。
シャワーを使って、部屋着で良いから着替えてくるように、と私に告げ、バルトフェルドは自らキッチンに立っていたらしい。
私同様、今は”世捨て人”状態の彼もクリスマスを祝うという気持ちはなかったらしく。メイド達には休暇を与えていたのだ、と聞いたのは食堂に降りて行ってからだった。
切り分けたチキン、鮮やかなオードブルに、いつもよく食べる温野菜をたっぷり沿えて。そのテーブルには二人分くらいに丁度良い、こぢんまりとした、鮮やかなフルーツで盛りつけられていたケーキがあった。
「あなたが?」
最後のセッティングを終えた彼が振り返った。
「祝うつもりがなくても。もたらされた美味い飯はきちんと頂かないと…作ってくれた人に失礼だからね?」
思わず、私は吹き出した。
「そうね、美味しそう」
この屋敷の食堂は本当に広くて。テーブルも、一体何人並んで食事ができるのかわからないほどだ。その、窓よりの隅に私達は腰を下ろし、ワインの栓を抜いて…何に、と言うわけでもなく無言で”乾杯”とグラスを鳴らした。
「今日の流星雨はまた、凄いね」
夕暮れ時から、ずっと見ていて飽きないほどだった、と彼は言う。
「そうね。でも仕事にならなかったわ」
「良いじゃないか。皆にはいいクリスマス休暇になっただろう」
ワインがおいしい。
そして、温められたチキンが口の中でほろっと解れた。
「オーブでもクリスマスは祝うのね」
「プラントだって、宗教的概念はもうどこかに行ってしまって、クリスマスはただクリスマスとしてある、という程度だ。皆、ポジティブに騒いだり、何かに感謝できるきっかけを欲しているんだろう。そんな機会は、多い方が良い」
彼らしい物言いに、私は笑って頷いた。
窓の外。海に降るほどの星。波はその光を映し、きらきらと揺れた。
無理のない程度に食事を進め、そしてケーキが入る余地を残してそれを終えた頃。
彼が席を立ち、いつもの儀式のようにコーヒーを入れ始めた。
「お疲れだろうから、カフェオレにするかい?」
「あら、良いの?」
「まあ…コーヒーの楽しみ方も人それぞれだ。美味いと感じてくれたらそれでいいさ」
温めたカフェオレボウルに、あらかじめミルクを入れておき、そこにオーバーアクションでコーヒーを注ぐ。
「部屋に持って行って召し上がるかね?」
「え?」
「ボクは甘い物が苦手だからね。これは君の分だ」
フレッシュクリームがつやつやして、いろいろな種類のベリーとのコントラストが美しいそのケーキを、そのままトレイに移して彼は言った。
「食べきれないわ…それに、太ってしまうじゃないの」
彼はトレイのマットの上にフォークとナフキンを並べ、カフェオレボウルを置いた。
「今も十分魅力的だが、君はもう少しふっくらしている方が良いだろう。きちんと食事を取ったことを見届けたからね、ボクも安心して眠れるよ」
「…アンディ」
「ゆっくりと、味わうと良い。アスハ家御用達のパティシエの腕は姫のご自慢らしいよ」
後かたづけは任せてくれ、と言って、彼はそのトレイを私によこした。
ふ、と。
私は不思議な想いに囚われた。
「どうして、私はあなたを好きにならないのかしらね…?」
同居して。
至れり尽くせりの心配りをしてくれる、今、一番身近なはずの異性。
知力も胆力も申し分ない。
こんなに魅力に溢れた人間が目の前にいて、どうして___?
「それが、恋というものだろう」
彼は、こともなげに言う。
恋…?
ああ。
どきん、と心臓が跳ねた。
「そう、ね」
恋。
「さあ、ゆっくりすると良い。ああ…寝る前には歯を磨くことを忘れずに」
子供じゃないわ、と小さく反論しそしてトレイを受け取る。
「ごちそうさま。…ありがとう、アンディ」
「お休み。明日はどうする?」
「いつもと同じ時間に起きるけど、でも多分明日もデブリのコンディションがこんなだったら、仕事にはならないわね」
「なら、この時間は…サンタさんから君へのプレゼントなんだろう。マリュー…おやすみ、メリー・クリスマス」
恋。
ああ___その言葉を、久しく封印していたような気がする。
どきん、と心臓が鳴る。
二人分のケーキ。
一緒に過ごしたことのないクリスマス・イヴ。
そうね、これはプレゼントなのかもしれないわね。
そう思って。
私は自室のバルコニーに向いた窓を開け放ち、星の海に身をさらした。
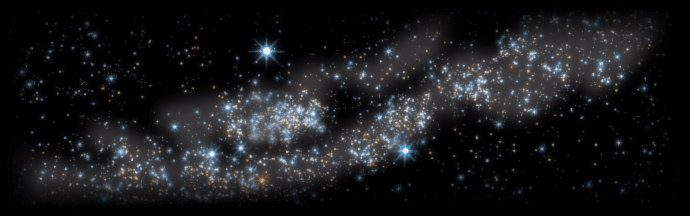
空を仰いで胸一杯に潮の匂いを吸い込む。
静寂。
波と、わずかに木の葉を揺らす風の音。
空から零れんばかりに降り注ぐ光の雨。
恋。
バルコニーのテーブルにトレイを置き、私は潮風が肌にわずかに冷たい、と感じたので、ガウンを取りに寝室にとって返した。
ふと。
クロゼットを開いて予備に置いていた毛布やクッションを一抱え取り出し、それをバルコニーのテラコッタの床に広げて、その真ん中に座り込んだ。
床の上にトレイをおろし、一口、カフェ・オレを含む。
まだ熱いそれは、配分が丁度良く…バルトフェルドの心遣いが浸みるように感じられた。
膝に、ケーキのプレートを取る。
たっぷりと盛られたとりどりの赤い果実の、宝石のようなその艶は、食べてしまうのが勿体ないくらいだった。
「甘い…」
こんな綺麗なケーキ、久しぶりだ…。
自分が、いかに潤いのない時間を過ごしているのかを実感させられてしまった、ような気がした。
舌の上に、果物の酸味と、絶妙なバランスのクリームの甘さが広がった。
今ここに…彼がいたら、きっと、大喜びでつつくだろうな。
口の端っこにクリームを付けたりして…。
そんなことを思うと、口元がふわりと緩んだ。
そう。
彼は、見かけからは想像出来ないくらい甘党で。
戦争のさなか、…あの悲惨な時期にでも、わずかに手に入ったスィーツを、大切に喜んで食べていたひと。
彼はよく食べて、よく眠る人だった。それをみなに茶化されることもあったようだけれど。
細胞のひとつ一つまでを酷使するモビルスーツの戦闘を繰り返していた彼らの疲労は、恐らく私達には理解できないほどだったのだろう。
そしてその糖分は全く贅肉と化すこともなく。
彼の命を支えていたのだろう。
”人間の脳は身体の2%しかないのに、摂取した糖分の20%を消費しちまうんだって。…だから、使った分とプラスアルファはがっつり食べないとね〜”
まるで、今耳元でその言葉を聞いたかのように、鮮明に思い出す彼の声音。
不思議ねえ。
むしろ自分の置かれている今が、幻のような気持ちになってくる。
控えめなクリームの甘さとラズベリーの香りが口いっぱいに広がって、私は長いこと忘れていた気持ちを取り戻していた。
手を伸ばして、カフェオレボウルを取り、それを両手で包むように持って温もりを感じながらゆっくりと飲み込む。
いつも、一緒に甘い物を食べるときには紅茶を入れていたわね。
”ああ、そうだな…”
あなた…気がつくと私の分もつまんでしまって…私もあのマカダミアナッツのクッキー、好きだったのよ?
”ゴメン!いや、ホント無意識でさー…”
ばか…。
くす、と笑い声が漏れた。
カガリご自慢のパティシエの腕は、確かに素晴らしかった。
ミルクの風味が絶妙のクリーム。
フルーツはぷりぷりに新鮮で、土台のスポンジも申し分ない。
幸せなケーキ。
そして、温かなカフェ・オレ。
見守っていてくれる人の気持ちの温もりが、そこにあった。
ああ。
確かに…この瞬間には感謝したい。
神様に求めるものはないけれど。
私は…。
トレイを部屋のテーブルに戻し、アンディの言いつけ通りに歯を磨き、ミネラルウォーターのボトルを取って、もう一度私はバルコニーに戻った。
降るほどの光は変わらずに帯を織り成し。
まるで世界中を子供達のために駆け抜けるサンタ・クロースのソリの軌跡のように、頭上に在り続けている。
素足に、テラコッタのタイルの感触はさすがに冷たかったので。
ありったけの毛布と、クッションを敷いて、ベッドに使っていた羽布団までを引きずってきて、それにくるまり、そのまま横になった。
仰向けになったら、まるで自分が星の海に浮かんでいるかのようだった。
瞬き続けている星だけではない。
沢山の流れ星が、まるで私に向かって降り注いでいるようにすら見えた。
綺麗…!
振り仰いだ空。
硬くて冷たい床の感触。
こんな眺め…私は見たことがある___いつのことだったろう?
記憶の糸をたぐり寄せると、唇が、無意識に懐かしい歌を紡いだ。
When you wish upon a star, makes
no diffence who you are …
わずかに身体を起こし、肩口まで羽布団を引き上げて、空を仰ぐ。
海の上だった。
砂漠を抜けて、AAがインド洋に出た頃だ。
束の間、ザフトの攻撃が止んで…夜、シフトの交代の後で、私は後部の甲板に出た。
そこに…あなたが、いた。
まだ、恋の予感すらなかったころだ。
しあわせなときは、たしかにあったのだ。
降り注ぐひかり。
硬質なその軌跡は、しかしとてもあたたかく胸に届く。
くす、と知らず笑みが零れた。
クリスマスの、奇蹟。
大人になったら…まして自分のような大人にはそんなものは望めないと思っていた。
でも。
このひかりは、平等に、地上にある全てのひとに降り注いでいる。
ああ。
あのひかりの中を…サンタ・クロースは今、どの辺りを駆け抜けているのだろうか?
膝を抱えて。
空を見上げた。
隣に、あなたが寝転がっているような。
そして、ふっと私を見て、微笑んでいるような気が、した。
また大きなひかりが流れ、一瞬稲妻のように空が白くなった。
ねえ。
ムウ…あなたはそこにいるのかしら?
その星の海の中に…もしくは、どこかで、同じ光の雨を、あなたも見ているのかしら?
あなたに出会わなければ…愛さなければ___とは、私は思わない。
出会えて、私はしあわせだった。
あなたを愛し、あなたに愛されて、私は…たしかにしあわせだった、と。
今もなお。
この恋は、私のたからものだ。
愛しているわ。
あなたのことを。
しあわせな気持ちで。
私は深い眠りに落ちた。
あたたかなひかりに包まれて。
潮風の匂い。
静かな夜。
静かに、星は降り続ける。
この作品の雰囲気が何とも言えず好きです。
対の作品がこちら